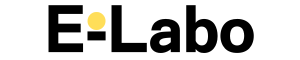現場のプロが語る!効率アップを実現する電材活用術
電気工事の現場では、いかに安全かつスピーディーに作業を進めるかが常に問われます。ベテランの電気工事士や現場作業員は、その経験と知識から、作業効率を劇的に向上させる「電材の選び方」「便利な工具との組み合わせ」「独自の時短テクニック」を知り尽くしています。
今回は、彼らが実践している「効率アップを実現する電材活用術」を、具体的な事例を交えながらご紹介します。日々の業務に追われる中で、「もっと効率を上げたい」「無駄をなくしたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
1. 電材選びの極意:使いやすさと汎用性がカギ
「電材はただ選ぶのではなく、その後の作業工程まで見越して選ぶことが重要」と語るのは、経験20年のベテラン電気工事士、田中さん。
a. ケーブル・電線の選び方:引きやすさと識別のしやすさ
「現場で一番時間を使うのが、実はケーブルの引き込み作業。だからこそ、滑りが良く、絡まりにくいシース(外皮)の材質を選びます。」と田中さん。特に、PF管やCD管に通線する際は、摩擦係数が低いケーブルを選ぶことで、大幅な時短に繋がるとのこと。
また、「多芯ケーブルの色分けが明確なものを選ぶのもポイント。例えば、VVFケーブルなら心線に白いラインが入っているものや、色鮮やかなものが識別しやすく、誤配線のリスクも減らせます。」と、結線作業でのミス削減にも言及します。
b. 端子・コネクタ:接続方法の多様性と信頼性
「圧着端子だけでなく、差し込み形コネクタやプッシュ式端子も積極的に活用します」と話すのは、通信工事を専門とする佐藤さん。
「特に照明器具の増設や改修では、差し込み形コネクタ(例:WAGOコネクタ)が非常に便利。ワンタッチで接続できて、ビス止め作業が不要になるので、高所作業での疲労も軽減されます。もちろん、信頼性も高く、増締め不要なのも魅力的です。」
c. 配管材:加工のしやすさと耐環境性
「PF管やCD管を選ぶ際は、柔軟性がありながらも潰れにくい材質を選びます。急なカーブでもスムーズに通線できるものが理想です」と配管工事のプロ、山本さん。
「屋外配管では、UVカット加工が施された耐候性の高い電材を選ぶことで、将来的な劣化による再工事のリスクを減らせます。少し初期コストが高くても、長期的に見れば効率アップとコスト削減に繋がります。」
2. 効率を最大化する工具との組み合わせ
適切な電材を選んだら、次はそれを活かす工具選びです。
a. 電動工具:コードレス化で自由度を向上
「以前は延長コードの取り回しに苦労しましたが、最近はほとんどの工具をコードレスにしました」と田中さん。インパクトドライバー、圧着工具、ケーブルカッター、ホールソーなど、バッテリー式の電動工具を導入することで、電源を探す手間やコードの準備・片付け時間がなくなり、作業のフットワークが格段に軽くなったとのこと。
b. ケーブルストリッパー:高精度で安定した作業を
「様々な種類のケーブルに対応できる多機能ケーブルストリッパーは、もはや必須アイテムです」と佐藤さん。「被覆剥きは手作業だとバラつきが出やすいですが、高精度なストリッパーを使えば、安定した品質で迅速に作業を進められます。特に大量の端子処理がある場合は、その差は歴然です。」
c. レーザー墨出し器・レベル:高精度な位置出しで手戻りをなくす
「照明器具やコンセントの高さ合わせには、レーザー墨出し器が非常に役立ちます。複数人で作業する際も、基準が明確なので、手戻り作業が格段に減りました」と山本さん。水平器と組み合わせて使用することで、より正確な位置出しが可能になり、最終的な仕上がりの美しさにも繋がるとのことです。
3. プロの時短テクニック:段取りと情報共有
電材と工具の選定だけでなく、作業の進め方にもプロならではの時短テクニックがあります。
a. 事前準備の徹底:段取り八分
「現場に着いてから『あれがない』『これがない』では時間の無駄。事前に必要な電材や工具をリストアップし、漏れなく準備するのが基本中の基本です」と田中さん。「特に、事前に寸法を測ってケーブルをカットしたり、端子を仮付けしておくなど、事前加工できるものは極力済ませておきます。これだけで現場での作業時間が半分以下になることもあります。」
b. 工具の配置と整理:導線を意識する
「工具箱の中も、作業中に迷わず取り出せるように整理整頓しています。使う頻度の高いものは手前に、滅多に使わないものは奥に、といった具合です」と佐藤さん。「また、作業中は使う工具を手の届く範囲に仮置きすることで、無駄な動きをなくし、集中力を維持できます。」
c. 作業員間の情報共有と役割分担
「チームでの作業では、互いの進捗状況を密に共有することが大切です」と山本さん。「例えば、一人が配管作業をしている間に、もう一人が通線準備を進めるなど、無駄な待ち時間が発生しないように役割分担を明確にします。図面チェックも複数人で行うことで、ミスを早期に発見し、手戻りを防げます。」
d. 「見える化」の徹底:ラベルとマーキング
「ケーブルには必ず行き先や用途を示すラベルやマーキングを施します」と田中さん。「特に改修工事では、既存の配線が入り組んでいることが多いので、明確な識別は必須です。後工程の作業者や、将来のメンテナンス時にも役立ちますし、誤配線のリスクを大幅に減らせます。」
まとめ
電気工事の現場で効率を上げるには、単に作業を速くするだけでなく、適切な電材選び、効率的な工具の活用、そして何よりも事前の段取りとチーム内の情報共有が重要であることが分かります。
今回ご紹介したプロの技は、どれも日々の業務で実践できるものばかりです。ぜひ、ご自身の現場で取り入れ、作業効率の向上と、より安全で質の高い電気工事の実現を目指してください。
皆さんの現場での「効率アップ術」があれば、ぜひコメントで教えてくださいね!