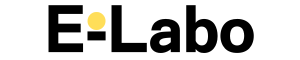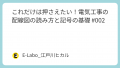電線の種類と選び方完全ガイド:VVF、CV、IVケーブルの違いと用途
電気工事やDIYを始める際、必ず直面するのが「どの電線を選べばいいんだろう?」という疑問です。ホームセンターに行けば様々な種類の電線が並んでいますが、それぞれに特徴があり、用途を間違えると感電や火災のリスクにもつながりかねません。
本記事では、電気工事で特によく使われる「VVFケーブル」「CVケーブル」「IVケーブル」の3種類に焦点を当て、それぞれの特徴、許容電流、電圧降下計算の基礎、そして適切な電線選定のポイントを分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたのプロジェクトに最適な電線がきっと見つかります。
電線とは?その役割と安全性の重要性
電線は、発電所から送られてきた電気を、各家庭や工場、オフィスで使うための機器へと届ける「電気の通り道」です。単に電気を流すだけでなく、私たちの安全を守る上で非常に重要な役割を担っています。
電線の主な役割
- 電気の供給: 必要な場所に安定して電気を供給します。
- 絶縁: 電気が外部に漏れ出さないよう、導体(電気を通す部分)がビニルやポリエチレンなどの絶縁体で覆われています。これにより、感電やショート(短絡)を防ぎます。
- 保護: 外からの物理的な力や熱、水などから導体を保護します。
電線選びを間違えると、発熱による火災、漏電による感電、機器の故障など、様々なトラブルの原因となります。そのため、用途に合った適切な電線を選ぶことが何よりも重要です。
主要な電線の種類と特徴
ここでは、特に使用頻度の高い3種類の電線について解説します。
1. VVFケーブル(Vinyl insulated Vinyl sheathed Flat type cable):一般住宅の屋内配線の主役

VVFケーブルは、正式名称を「600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形」といい、その名の通り、導体をビニルで絶縁し、さらにその上をビニルで覆った平たい形状のケーブルです。一般住宅や小規模店舗の屋内配線で最も広く使われています。
- 特徴:
- 形状: 平形(フラット)で、電線が2本または3本(アース線含む)並行に入っています。
- 絶縁・シース: ビニル(難燃性あり)。
- 柔軟性: 比較的硬めですが、手で曲げることも可能です。
- 施工性: シースを剥がすのが比較的簡単で、住宅の壁内などに通線しやすい。
- メリット:
- コストパフォーマンスに優れる。
- 屋内での施工実績が豊富で、情報も多い。
- 自己消火性があり、燃え広がりにくい。
- デメリット:
- 屋外や地中での直接埋設には不向き(別途保護が必要)。
- 柔軟性が低く、細かい曲げ加工には不向き。
- 主な用途:
一般住宅や店舗の分電盤から、照明器具、コンセント、スイッチへの屋内配線全般。
2. CVケーブル(Cross-linked polyethylene insulated Vinyl sheathed cable):高圧・低圧の幹線配線の主力

CVケーブルは、正式名称を「600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル」といい、導体を架橋ポリエチレンで絶縁し、ビニルでシースしたケーブルです。VVFケーブルよりも高い電圧や大きな電流を流す場所、特に建物の幹線(メインの配線)や屋外配線で広く使用されます。
- 特徴:
- 絶縁体: 架橋ポリエチレン(耐熱性・電気的特性に優れる)。
- シース: ビニル。
- 柔軟性: VVFケーブルよりもしなやかで、取り回しがしやすい。
- 耐熱性: 架橋ポリエチレンの特性により、許容温度が高く、大電流を流すことが可能。
- 耐水性・耐候性: 屋外や地中埋設にも適しています(直接埋設可能なタイプもある)。
- メリット:
- 大電流に対応でき、発熱しにくい。
- 耐久性が高く、寿命が長い。
- 屋外や地中など、過酷な環境にも対応できる。
- デメリット:
- VVFケーブルよりも高価。
- 絶縁体を剥がすのに専用工具が必要な場合がある。
- 主な用途:
建物への引き込み線、分電盤までの幹線、工場やビルなどの動力配線、屋外配線、地中埋設配線。
3. IVケーブル(Insulated Vinyl cable):盤内配線や電線管内の引き込み線

IVケーブルは、正式名称を「600Vビニル絶縁電線」といい、導体をビニルで絶縁しただけの単心電線です。単体では使用せず、主に電線管(PF管、VE管など)に通したり、分電盤などの盤内配線に使用されます。
- 特徴:
- 絶縁体: ビニル。
- 形状: 丸型の単心電線。シースはありません。
- 柔軟性: 比較的柔らかく、曲げやすい。
- 色: 赤、黒、白、緑(アース用)など、様々な色があり、識別に便利です。
- メリット:
- 安価で、色による識別が容易。
- 電線管に通すことで、物理的な保護と安全性を確保できる。
- 盤内での狭いスペースにも配線しやすい。
- デメリット:
- シースがないため、単体で露出配線することはできない(必ず電線管などで保護が必要)。
- 耐水性や耐候性は電線管に依存する。
- 主な用途:
分電盤や制御盤などの盤内配線、電線管内を通す屋内外の引き込み線、アース線。
許容電流:電線選定の最重要ポイント

許容電流とは、電線が安全に流すことができる最大の電流値のことです。この許容電流を超えて電流を流すと、電線が発熱し、絶縁体の劣化や焼損、ひいては火災の原因となります。電線を選ぶ際には、接続する機器の最大電流値(または消費電力から計算)が、選定する電線の許容電流以下であることを必ず確認しなければなりません。
許容電流に影響する主な要素
- 電線の導体サイズ(断面積): 太い電線ほど多くの電流を流せます。
- 絶縁体の種類: 耐熱性の高い絶縁体(例:架橋ポリエチレン)ほど、高い許容電流を持つことができます。
- 周囲温度: 周囲の温度が高いと、電線の放熱が妨げられ、許容電流が下がります。
- 敷設方法: 電線管に複数本まとめて入れる場合や、密閉された空間に敷設する場合は、放熱性が悪くなるため、許容電流が下がります(電流減少係数を考慮)。
【目安の確認方法】
各電線のメーカーカタログや、電気技術基準、内線規程などに許容電流表が記載されています。必ずこれらの資料で確認しましょう。
電圧降下計算の基礎:電気の「勢い」を保つために
電線に電流が流れると、電線の抵抗によって電圧が少しずつ下がっていきます。この現象を「電圧降下」と呼びます。電圧降下が大きすぎると、機器が正常に動作しなかったり、性能が低下したりする原因となります。
電圧降下が発生するメカニズム
電線の抵抗 (R) と流れる電流 (I) によって、オームの法則(V = I × R)に従って電圧降下が発生します。長い距離を流すほど、または細い電線ほど抵抗が大きくなり、電圧降下も大きくなります。
電圧降下の許容範囲
日本の電気設備技術基準では、低圧の屋内の幹線や分岐回路において、電圧降下の許容値が定められています(通常、標準電圧の数%以内など)。
電圧降下を抑えるには
- 電線を太くする: 抵抗が減り、電圧降下を抑えられます。
- 電線の長さを短くする: 抵抗が減り、電圧降下を抑えられます。
【簡易計算の考え方】
正確な電圧降下計算は専門的ですが、基本的な考え方としては、電線の抵抗値(線材の材質、断面積、長さによって決まる)と流れる電流から、オームの法則を応用して計算します。長距離配線や大電流の回路では、必ず電圧降下を考慮して電線を選定する必要があります。
適切な電線選定のポイント
これまでの内容を踏まえ、電線選定のポイントをまとめます。
- 用途と敷設場所を確認する:
- 屋内配線(壁内・天井裏):VVFケーブル
- 幹線、屋外、地中:CVケーブル
- 電線管内、盤内配線:IVケーブル
- その他、耐熱性、耐水性、耐油性など、特殊な環境要件があるか確認。
- 流れる電流値(または消費電力)を確認する:
- 接続するすべての機器の最大電流(A)または総消費電力(W)を把握します。
P(W) = V(V) × I(A)の公式から、必要な電流値を計算できます。
- 許容電流を確認する:
- 算出した電流値に対し、選定する電線の許容電流が十分であるか、メーカーのカタログや基準で確認します。
- 敷設方法(複数本まとめ配線など)による電流減少係数も考慮に入れます。
- 電圧降下を考慮する:
- 配線距離が長い場合や、精密な機器を接続する場合は、電圧降下を計算し、許容範囲内であることを確認します。必要に応じて太い電線を選びます。
- 将来の増設を考慮する:
- 将来的に機器が増える可能性がある場合は、少し余裕を持ったサイズの電線を選んでおくと、後々の変更が容易になります。
- 資格の要不要を確認する:
- 屋内配線などの電気工事は、電気工事士の資格が必要です。無資格での作業は法律で禁止されており、非常に危険です。専門業者に依頼しましょう。
まとめ:安全と効率のための電線選び
電線は、私たちの生活を支える電気インフラの根幹をなす部材です。VVFケーブル、CVケーブル、IVケーブルといった主要な電線の特徴を理解し、許容電流や電圧降下といった重要な要素を考慮して適切に選定することが、安全で効率的な電気設備を実現する鍵となります。
「これで大丈夫かな?」と少しでも不安に感じたら、決して無理はせず、必ず専門の電気工事士に相談するようにしてください。正しい知識と安全意識を持って、快適な電気ライフを送りましょう!
電線選びで迷った時は、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。